第15回 ITeens Lab文化祭に見る、子どもたちの本気と学びの未来|2日間のすべてと代表の思いを徹底レポート!
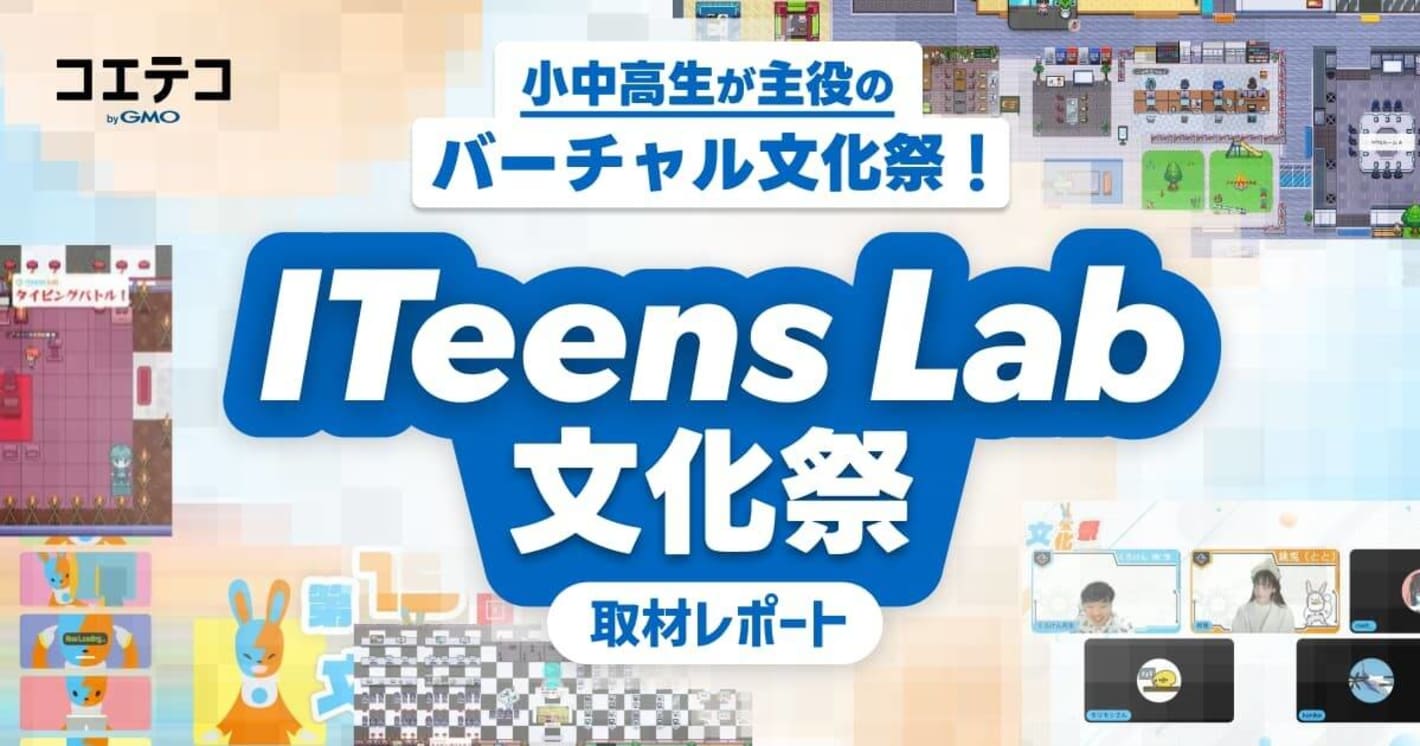

文化祭はYouTube生配信と、バーチャル空間「MetaLife」を組み合わせた形で実施され、生徒たちはそれぞれのスタイルで自由に参加。応援コメントを送ったり、配信を見ながらゲームで遊んだり、タイピングバトルに出場したりと、思い思いの方法で文化祭を楽しみました。

バーチャル空間「MetaLife」
また、生徒主催の企画コーナーがあるのも大きな特徴。まさに「文化祭といえばこれ!」と思える、生徒発信の盛り上がりが各所で見られました。
そこで今回は、ITeens Labならではのオンライン×リアルが交差する濃密な2日間をたっぷりレポート!
さらに、ITeens Lab 代表・古林先生、共同代表・近藤先生にもインタビューを実施。教育理念やカリキュラム、文化祭を通じた教育への想い、そしてこれからの展望について伺いました。
「子どもに合う学び方を探している」「ITやプログラミングに興味はあるけど、どんな力が育つのか知りたい」そんな方は、ぜひ最後までご覧ください。
第15回 ITeens Lab文化祭 概要
本編のレポートに入る前に、まずは第15回 ITeens Lab文化祭の概要をご紹介します。ITeens Lab文化祭は、ITeens Labで学ぶ小学3年生から高校3年生までの生徒たちが、自らの作品を発表し、交流しながら楽しむオンラインイベントです。

カリキュラムは4か月ごとのターム制で、文化祭も4か月に一度、定期的に開催。
さらに文化祭オリジナル企画や生徒主催の企画など、まさに学校の文化祭さながらの盛り上がりを見せる一大イベントです。
・ライブ配信(YouTube)時間:両日 13:00〜18:00
・文化祭会場(MetaLife)一般開放時間:3/23(日)10:00〜12:00
・スペシャルゲストMC:YouTubeゲーム実況者 跳兎(とと)さん
1.作品発表
生徒の作品紹介
先生の作品紹介
保護者の作品紹介
2.生徒企画ブース
ピクトセンス
スマブラトーナメント
ITLバンカラスプラ杯
闇鍋人狼オンライン
AmongUs
KRUNKER最強王決定戦
3.文化祭企画
タイピングバトル
マインクラフト同好会
VR Chatワールド
ゲームセンター
フリーホワイトボード
観客投票
今回もUnity作品や動画制作、音楽制作、3Dモデリングなど、多彩な作品が発表されています。
さらに、先日開催されたハッカソンの作品発表に加え、新たな試みとして保護者による作品発表も行われました。

文化祭の様子はYouTubeから生配信され、バーチャル空間「MetaLife」では実際に生徒の作品で遊んだり観覧したりもOK!
第12回大会からは、生徒や保護者だけでなく外部の方も参加可能になり、より多くの人が生徒たちの作品や活動に触れられる場となっています。
常に進化を続けるITeens Lab文化祭、背景にある教育理念や運営の裏側については、後ほどインタビューパートでお伝えします。
まずは早速、文化祭の様子を見ていきましょう!
文化祭の幕開け!生配信はコメント欄も大盛況
YouTubeでの生配信では、開始前からコメントが続々と投稿され、期待感が高まる中でカウントダウンがスタート。オープニング映像は、まるで映画のプロローグを思わせるような演出から始まります。静寂の中から徐々に音が立ち上がり、やがてエネルギッシュで疾走感あふれるビートが響き渡ります!

オープニング映像・音楽は、生徒と先生が手掛けた作品
音楽の波が視聴者を一気に引き込み、熱気が高まったところで、いよいよMCくろけん先生と、ゲストMCのゲーム実況者・跳兎(とと)さんによるオープニングトークへ!

MC:くろけん先生、ゲストMC:跳兎(とと)さん

その頃、MetaLife内の控室では、最初の発表を控えた生徒たちが集合。引率の先生が点呼をとる様子は、まるでリアルな学校の文化祭のようです。発表直前の生徒に話を聞くと、「緊張はそこまでしていない」との声も。

MetaLifeでは、アバター同士が近づくと会話ができる!
この日のために、作品づくりはもちろん、プレゼンや資料作成にも力を注いできた生徒たち。発表を前にした控室にはほどよい緊張感が漂うかと思いきや、意外にも和やかなムードの中で開始時間を待っていました。
生徒作品紹介|研究室ごとに展開された、個性あふれる発表の数々
文化祭のメインコンテンツのひとつが、生徒による作品発表です。ITeens Labには一般教養クラスや研究室と呼ばれるクラスなどがあり、担当講師がサポートを担当します。文化祭では、まるで大学のゼミ発表のようなスタイルで、それぞれ個性あふれる作品が披露されました。
ここからは、いくつかの発表をピックアップしてご紹介します。
音楽制作|リミックスからキャラ設定まで、音と世界観を作りこむ
トップバッターを飾るのは音楽制作クラスです。流行曲のリミックス作品や、オリジナルキャラクターの世界観を音で表現する作品などが披露されました。
「とよ研」(とよ先生による研究室)による作品発表
最初に紹介されたのは流行曲をテーマにした制作で、ベース・ドラム・ボーカルなどに分けてトラックごとに編集したそう。クラップにエコーをかけたり、パーカッションを差し込んだりと、音の質感や構成を自由にアレンジするリミックス風のアプローチが見られました。

生配信上で、視聴者も一緒に作品を視聴。
また、他の生徒については、制作中にスランプに陥っていたとのこと。制作の裏には思わぬ苦労もあったようですが、諦めず、和音の組み合わせを試行錯誤した思い出を語ってくれました。

左下コメント欄:生徒同士の声援もあり、温かい雰囲気です。
高校生のある生徒は、前回の発表で「スマートフォンからは低音が聞こえづらい」と気づき、音のバランスを見直したそう。ベース音を意識的に調整した結果、「今回はよく聞こえたはず」と自信を持って発表していました。


キャラクターの造形や資料作りにも力を入れた姿勢に、コメント欄からは称賛の声が!
アニメーションの動きをつけた手描きのキャラクターについては、「裏ボスにしたいキャラなんです」と話すなど、音とビジュアルを一体にした世界観の構築も見事でした。
クリエイティブ基礎・中級・女子限定|クイズにWebサイトにゲーム制作、表現の幅が広がる!

次のパートではクリエイティブ基礎・中級・女子限定などに所属する生徒が、クイズ制作やWebサイト制作、ゲーム開発など多彩な作品を発表しました。
使用ツールもScratchやUnity、Canva、Visual Studio Codeなど幅広く、発表からもそれぞれの関心や得意分野が見えてきます。
プログラミング中級クラスのある生徒は、架空の国の外務省Webサイトを制作。

WebサイトはVisual Studio Codeで作成!今後のコンテンツ拡充を期待する声も。
「より国の存在をリアルに感じられるように」との思いを込めて、国旗はアイビスペイントで自作し、Webサイトはアップロードまで行いました。
外務省のHPってちゃんと見たことなかったかも!
こちらはScratchを使ったオリジナルゲームの発表です。

手描きのエフェクトが毎回変化し、攻撃パターンも複雑に作りこまれているため、飽きずに楽しめる設計に。
その場でMC・くろけん先生がプレイしますが、残念ながら負けてしまいます。

複雑な設計で、飽きずに取り組める仕様に
私が事前にやったときは勝てました(笑)同じ攻撃をしてこないので、設計も複雑なはず。ギリギリのダメージバランスが良いですね!

ITeens Labの設立日クイズ(答えは2013年8月10日)
設立日に関するクイズでは、「2013年って、オレ2歳」「ITeens Labは、みんなが赤ちゃんの頃にできたのかも」と、配信上で笑いと発見が生まれていました。
なかにはUnityのゲームを専用サイト「Unity Play」にアップロードしている生徒もおり、制作から発信までを一貫して経験している様子が伝わってきました。

動画制作クラス|映像×音楽×仲間の力で伝える、「好き」が詰まったクリエイティブ
文化祭の中でもひときわコメント欄の流れが速く、盛り上がりを見せたのが動画制作クラスです。Adobe Premiere Proなどさまざまなソフトを使って編集された映像には、日常の風景やネット動画、ゲームのプレイ画面などが組み込まれ、生徒一人ひとりの思いが詰め込まれた作品が並びました。

こちらの生徒は、友達が描いたイラストをもとにした合作映像を発表。たにえん先生によると、動画制作クラスでは生徒同士のコラボレーションも多く、チーム制作の面白さが活きているようです。

こだわりポイントは、「画面が切り替わるたびに口の動きが変わる演出」とのこと。
映像と音のタイミング、表情の変化にまで気を配った細かな演出に、MC陣からも称賛の声が挙がります。
(素材を外注して映像を作る流れは)もう、「仕事をしている人」のやり方ですね!
制作歌詞のタイミングに合わせてテロップを入れるスタイルで、スポーツと音楽の融合を目指した意欲作に。

「次のオリンピックで卓球に興味を持つ人が増えたらいいな」との思いが込められた作品
初参加で、ここまで仕上げてくるとは思いませんでした!
映像に合うシーンを探して、構成を練って、編集して……!愛を感じました。
最後に披露されたのは、クラス全員による合作作品です。

50か所のパートを一人ひとりに割り振って制作された超大作!
感想の一つひとつから、作品づくりの大変さと達成感、そして何より充実した時間を過ごしたことが伝わってきます。

今期の集大成となる合作動画の最後には生徒、先生の感想も
動画制作クラスの発表を観たあとは、圧倒されるね……。

MetaLifeでは、一つ一つのPCなどから生徒の作品にアクセスできるようになっています。
3Dモデリング|作りたいものを、作り続ける!質感・構造・世界観へのこだわりを表現
3Dモデリングクラスは、2日間にわたって発表が行われた人気クラスのひとつ。
引率は、ITeens Lab 共同代表のドゥー先生こと近藤先生
使用ソフトはBlender(ブレンダー)が中心で、動画制作やデザインなども含む自由度の高い作品づくりが展開されました。
中には1タームで何作品も制作する生徒もおり、完成度の高さから「そのままゲームに登場しそう!」とコメントが飛ぶ場面も。
冒頭ではバルーンドッグをモチーフにした3D作品が発表されました。半透明のつるつる・ふわふわとした質感がしっかり表現されています。

こだわったポイントは「バルーンの結び目」「耳の位置」とのこと
バルーンドッグはFBXファイル(3Dモデルの保存形式)で書き出して、VRワールドに実装済み。しかも、かなり巨大サイズで配置しているんだとか!
透明感のある作品ってなかなかないですね。軽やかで、マテリアルの設定に対するこだわりを感じます。
前に制作されたメロンクリームソーダも透明感のある作品ですね。
「小さなキャラクターが大きな武器を持っている」ギャップがユニークで、武器のチューブ部分の曲線をどう表現するかに苦戦したとのこと。

VRワールド内では実際に「持てる」仕様で、構えることを想定した作り込みに。
次に、Blenderで麻雀牌を制作した生徒が登場!
ひとつひとつの牌には模様が彫り込まれており、「3Dプリントすれば実際に麻雀ができるクオリティ」と、視聴者を圧倒します。

制作した生徒いわく、難易度の高さから泣く泣く制作できていない牌もあるそうで、今後の制作に期待が寄せられます。スキルの高さはもちろん、意外性やオリジナリティといったクリエイティビティが光る作品でした。

制作の裏側を聞けるのも文化祭ならでは
子ども達に「好きなことやってみて」って言うと、予想外の作品が生まれて面白いんですよね!
モデルを選んだ理由は、「見た目がシンプルで作りやすそうだったから」とのことですが、完成度の高さに、鉄道運転シミュレーションゲーム「電車でGO!」を彷彿とさせるといったコメントも。

画像右側、連結部分はとにかく細部にこだわったそう
作品はRobloxで動作可能な状態にまで発展。「制作中には電車がプルプル跳ねてしまった」と、謎の挙動に悩まされたエピソードも披露されました。

Roblox内では作品が動き、車内に入れます。音や電気が点く仕様まで実装済み。
その他にも、赤くて質感の美しい洗濯機をモデリングした作品など、生徒たちの情熱と個性が詰まった3Dモデリング作品が発表されました。

個性豊かな作品の数々
クリエイティブ基礎|好きを共有し、楽しく知識を深め合う
クリエイティブ基礎クラスは、プログラミングにとどまらず、自分が夢中になれる分野を見つけて表現することを目的としたカテゴリーです。今回はCanvaを使ったクイズ作品が多く、生徒自身も配信画面に登場してクイズを解き、会場を盛り上げました。
クイズのテーマは実に多彩で、漢字、鉄道、アニメ、川の名前、推し、カラーコード、くしゃみの止め方クイズなど幅広い内容が展開されました。

こちらの「国旗クイズ」は、スライドの背景に赤、文字には黄色を使用し、中国の国旗をイメージした配色も注目ポイントのひとつ。

高校世界史レベルの出題も!
MC・くろけん先生からは配色についてアドバイスがあったそうで、デザインスキルも随所に光ります。他作品においても、選択肢の文字にはトピックに関連する色を使うなど、統一感や視認性への配慮も目立ちました。
先日教えたことを早速実践してくれて、嬉しい!
クイズのフォーマットを通して、伝える力や調べる力、考える力など、教養的な視点も身につくクラスとしての側面が強く伝わってきました。

クラス内で制作した3Dモデルも発表
ガチ開発|自由度MAX!オールジャンル開発
ガチ開発クラスは、DiscordのBOT、Webアプリ、スマートフォンアプリ、3Dモデリングなど、オールジャンル!Blenderで制作した「犬が歩くアニメーション」を発表した生徒は、犬が左右に揺れる動きを丁寧に再現。さらに、ゲームマップに対応した地形の生成にもチャレンジ中で、自力で地形を作れるようになりたいと語っていました。

くろけん先生が7作品を1つのスライドにまとめて発表!発表方法もさまざまです。
Blenderでの作品づくりをきっかけに資格取得に挑戦した生徒もいました。くろけん先生はCADが得意だそうで、サポートを受けながら、実際に3次元CAD利用技術者試験の2級に合格したとのこと!

くろけん先生のサポートと共に、3次元CAD利用技術者試験の2級に合格!
驚きの声が上がったのが、Googleサイトを使って制作された架空国家の公式サイトです。

全35ページの超大作!遊び心と構築力が融合した傑作品。
鉄道を中心に、歴史や建築物、インフラ、国民生活保護情報にいたるまで細かく設計されており、旅行パンフレットのような構成でわかりやすくまとめられています。
ロゴやお問い合わせフォームまで完備された作り込み具合に、絶賛のコメントが飛び交います。
Unity|見せ方までこだわり抜いた!怒涛のUnity発表タイム
Unityクラスには複数の研究室が所属しており、それぞれ空気感や担任の得意分野に応じた色が出るのも特徴です。リズムゲームやシューティングゲーム、アスレチック、VRチャットステージ、江戸時代の単位を使った計算ツールなど、バラエティ豊かな作品が続々と登場しました。

「空をフィールドにしたアスレチックゲーム」を発表したのは、今年に入ってITeens Labに参加したばかりの生徒。入会からわずか3ヶ月でここまで作れるようになったという成長スピードに、MCも驚きの声を上げていました。

キー操作やジャンプのアクション要素もあり、「次は音も入れてみたい」とのこと。
別の生徒が手がけたのは、スライムを倒して進むアクションゲーム。

マップには、国土交通省が公開している3D資料を活用。実在の地形データを組み込む本格派!
23体倒すとクリアになる設計で、攻撃が当たると敵キャラが白く光り、飛び散る演出も。完成度の高さに、コメント欄も大盛り上がりでした。
また、ジャンプした瞬間にカメラが下からの視点になるこだわりで、スピード感あふれる痛快な仕様です。
爽快感はゲームにおいてとても大事なポイントですね!
また、Unityクラスの魅力は、ゲームの内容だけにとどまりません。
「どう見せるか」「どう伝えるか」にも、ひとりひとりが全力を注いでいるのが印象的で、カメラアングルやUI設計の意図を丁寧に語る生徒も。

カメラの揺れ感を駆使したイメージ映像では、編集力の高さも絶賛
作品の中身だけでなく、見せ方にも全力を注いでいるのが印象的でした。

追従カメラツールを使用した作品も
操作性についても、「ただの連打より、左右交互の連打の方が有効」など、プレイヤーの操作性を意識した細やかなこだわりが光る作品もありました。

アイテムを選択すると、白い吹き出しが出る仕様
自由枠|自分の“好き”を、好きなかたちで。分野を超えて広がる表現の世界
ジャンルに縛られず自由な発表ができる自由枠では、「Blenderでコンビニを作りました」と発表する生徒もいれば、「文化祭クイズ」や「VR Chatの空間づくり」に挑戦したと語る生徒も。動画作品として注目を集めたのが、Minecraftのクリエイティブワールドを使った「北ノ宮」都市の紹介動画。

ITeens Labのマイクラサーバーで生徒たちが共同開発中の架空の都市、「北ノ宮」
「北ノ宮」では、生徒主催の万博も開催されたそうで、現在はPVP会場(プレイヤー同士が戦って遊べる会場)になったとの情報も公開されました。

リアルさと遊び心が絶妙に混ざった仕上がりに会場もコメント欄も大盛況!
PVP会場!?先生も知らない情報だ……!
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://iteenslab.com/event_report_itlexpo01/ >
さらに、こちらは「文章の書き方」をテーマにしたスライド発表です。

発表した生徒は、Discordでのやりとりや、文化祭の感想文を書く場面をふまえ、「どうすれば文章力が上がるか?」という視点から、テキストコミュニケーションのコツや文章作成のTipsを紹介。

どんな作品でも発表できる文化祭の自由さと、生徒一人ひとりの興味関心の多様さが垣間見える印象的なプレゼンでした。
さらに、自由枠で特に注目を集めたのが、cheeseさんが制作した「バトルタワー」。

PhotoshopやExcelなども駆使しながら、1年もの制作期間をかけて完成させた本作。
PC版だけでなくスマートフォンにも対応しており、その完成度の高さにMCも視聴者も言葉を失うほどでした。

ゲームの仕様は、ポケットモンスターの「バトルファクトリー」をもとに構築したそう
さらに、大量の種族値データの組み込み、ドット絵の制作、プレイ中に見つかったバグへの対応まで、本気の開発現場さながらの試行錯誤が詰まっていました。
新コーナー!保護者作品紹介|学びを親子で楽しむ取り組み
今回の文化祭では、保護者による作品も2点紹介されました。
1作品目は、Blenderを使ったオリジナルアニメーションです。なんとこちらの保護者は、アニメーション制作が初めてとのこと。
7ヶ月間の学習を通して得た知識を活かして、ぶつかった瞬間にカメラが揺れる演出や、アクションに合わせた躍動感ある動きを見事に表現していました。

動きの迫力に、コメント欄も大盛り上がり!
制作中には、1秒間に24フレームの重たい構成ゆえ、再生が追いつかない問題にも直面。低解像度で仮レンダリングを試したり、サンプル数を調整したりと、負荷を減らす工夫も取り入れながら制作を進めたそうです。

武器も自作しており、保護者の情熱が炸裂!
2作品目はショート動画の発表。人気ゲーム「Fortnite(フォートナイト)」を題材にしたパロディ作品で、編集やオチ作り、声の入れ方にも悩みながら完成させたとのこと。

YouTubeチャンネルも運営されているそうで、YouTubeにいくつか投稿したところ、24,000回再生を記録した作品もあったとのこと。MC陣からも、思わず「強い!」と、心の声が漏れてました。
新コーナー!ハッカソン|たった2日で!アイデアから作品へ、22世紀の秘密道具を制作
今回、ITeens Labの文化祭では、もう一つの新しい試みとしてハッカソン企画が実施されました。テーマは「22世紀の秘密道具」で、アイデアを短期間で形にしてプレゼンまで行う濃密なプロジェクトです。
「もし未来にこんな道具があったら?」を形にするプロジェクト
参加生徒たちは、得意なツールや、逆に「触ったことないけど挑戦したい」ツールにもトライしながら、2日間でアイデアスケッチから資料制作、作品発表までやりきりました。
まずは冒頭、「22世紀に必要なのは、(平和を守る)戦闘ロボット!」と語った生徒が制作したのは、「strubot(ストラボット)」。

プレゼンは「22世紀のイメージ、どう思いますか?」の問いかけから始まり、パンチやキックを使った本格アクションの演出に、視聴者も引き込まれていきました。
アニメーションにはBlenderを使用。ウェイトペイントやボーン設定に苦戦しながらも、実際のアニメーション技術に活用される誇張表現を学び、迫力あるモーションを完成させたとのこと。

大きな腕でダイナミックさを表現。加速スピードの調整も。
パンチの加速を途中で変えたり、右手に連動して足も動かす工夫をしたり、一緒に試行錯誤しましたね。

生徒のアイコンはキャラクターのアイデアスケッチ。作品作りへの愛を感じる。
次の生徒は、Blender歴2年ながらCanvaは初挑戦。そんな中で発表されたのが、ゲームのルールでもめないように整理してくれるロボット「くまさん」です。
ゲームで遊ぶ際、ローカルルールで揉めないために必要!といった熱い思いと共に、プレゼンを行いました。

衣装のディーラー風デザインやCM風の映像制作など、細部までこだわりが詰まった発表です。

衣装のディーラー風デザインや読み上げ音声など、細部までこだわりが詰まっています。これはぜひ商品化を…!
Blenderで作ったロボットに、VOICEVOXの音声を組み合わせてCM風に仕上げた映像は、まさに短期間とは思えない完成度。
この商品、実際にありそう!
等価交換ドアは、物を差し出すと“同じ価値のもの”を返してくれる未来の道具です。Blenderでドアのビジュアルを作成し、ちょっと不気味な「顔」を埋め込んでリアル感を意識したんだとか。

ドゥー先生(近藤先生)による等価交換ドア。右側の「顔」に注目……!
さらに驚きなのは、ChatGPTを埋め込んだWebサイトまで開発した点。画像をアップロードすると、そのモノの価値をAIが判定して“等価”な別のアイテムを提案してくれる仕組みです。

iPhoneをアップすれば15万円相当の品が返ってくる(!?)、まさに22世紀感満載の作品です。
「2日でここまで!?」と声があがるほど、短期間での発表とは思えない完成度の高い作品が次々と登場したハッカソン。まずやってみることの大切さや面白さが詰まった企画となりました。
生徒企画・文化祭企画
今回の文化祭では、配信内だけでなく、MetaLife上でも多彩な企画が実施されました。生徒企画
・スマブラトーナメント
・ITLバンカラスプラ杯
・闇鍋人狼オンライン
・AmongUs
・KRUNKER最強王決定戦
MetaLifeの一角は生徒企画ブースになっており、時間になると参加希望の生徒が集合します。

各ブースのデザインや看板制作も生徒が担当。集客も生徒主体です。
ピクトセンス企画の開始時間になると生徒達が続々と集合!「いま練習してます!画面共有しますね」「部屋また作りなおす?」とその場を仕切り、参加者に声をかけながらスムーズに運営していました。

先生の「もう始めてる?」という問いかけにも、「いま始まってます!」と落ち着いたやり取りで応じていました。

「スマブラトーナメント」
当日はタイムテーブルが変更される場面もありましたが、生徒たちは臨機応変に対応。「次の発表があるから○分までには行かないと」「今のうちに参加者を集めよう」など、自分たちでスケジュールを意識しながら進行していく姿が印象的でした。
中には、取材が入っても動じることなく受け答えをしてくれる生徒もおり、その頼もしさに驚かされます。

「ITLバンカラスプラ杯」
自分たちで企画し、準備し、当日の進行もしていく。そんな文化祭の裏側には、実は“働く”ことに近いようなリアルな経験が詰まっていて、生徒たちが大人顔負けの企画力と対応力を発揮していました。

「AmongUs」

「闇鍋人狼オンライン」
文化祭企画
さらに、ITeens Lab文化祭では「文化祭企画」として、誰でも自由に参加できる遊びと交流の空間が設けられています。・マインクラフト同好会
・VR Chatワールド
・ゲームセンター
・フリーホワイトボード
こちらはITeens Lab文化祭ではおなじみとなった、先生オリジナル開発のタイピングバトル。

注目のタイピング王の生徒が登場したエキシビションマッチでは、「勝つために頑張ってきました!3連勝したい!」と意気込みを語り、対する生徒からは「もう練習しないでくれ!」と、思わず笑ってしまうやり取りも。

ITeens Labならではの文化と遊び心が光る!
他の生徒は、「結構頑張ってます!トップ5に入れたから、トップ3を目指したい!」と語るなど、ランキング上位を目指す熱気と、コミュニティ内のノリが一体となった盛り上がりに。

出題テーマには「身内ネタ」もふんだんに盛り込まれている。
「バトル」と名付けられた企画ではありますが、どこか温かい空気が流れる企画でした。
さらにこちらは、Minecraftワールド中継の様子です。

ITeens Labでは、授業外で「マイクラ同好会」が自主活動を行っているそうで、先生はあくまで顧問の立場でサポートとして介入しているとのこと。

生徒の集合写真(ITeens Labのマイクラワールドにて)
現在、ITeens Labのマイクラワールドでは「国」がいくつも誕生しており、憲法を定め、通貨を発行し、外交や貿易、時には戦いも起きる独自の世界が築かれています。
先生から与えられる教材ではなく、Minecraftを通して自ら学び、表現する姿はまさにITeens Labの理念を体現するものです。
表彰の前に!生徒主体で計画中の「部活動」プロジェクト紹介
表彰に入る前に、ITeens Lab内で新たに始まる「部活動」についての紹介が行われました。発表してくれたのは、生徒のNETAKEさん。生徒でありながら、まるで先生のような立ち位置で、しっかりとプロジェクトの内容を伝えてくれました。

部活動は、生徒主体で運営されており、年齢制限なし・先生の参加もOK!
さらに活動場所や活動時間も、生徒たちが相談して決めるスタイル。普段の授業ではできないテーマを、意見を交わしながら一緒に探究していく場になっていく予定だそう。

部活動の概要
「こういう部活を作ってみたい」という声が先生からあがっていることもあるそうで、立場に関係なくやりたいことを形にできるのが特徴です。

アンケートフォームを活用して生徒達の意見を集めている。
ルールの詳細は後日公開予定だそうで、設立・入部希望はフォームから気軽にエントリーできるとのこと!表彰式の前にふさわしい、これからのITeens Labを形づくっていく新たな企画が紹介された時間でした。
さぁいよいよ次は、お待ちかねの表彰式です!
ドキドキの表彰へ!選ばれた作品は?
文化祭の最後を締めくくるのは、お待ちかねの表彰式!MCや視聴者によって選ばれた、心に残る作品たちが発表されました。
どの作品も素晴らしすぎて、選べない……!

MC・くろけん先生が選出したのは、たにえん研究室の合作チーム!

たにえん研究室のみなさん

ボーカロイド曲「のだ」を題材にした圧巻の映像でした。
ボーカロイド楽曲をピックアップし、一致団結して映像を制作した姿勢が高く評価されました。くろけん先生より、「このクラスの右に出るものはいないのでは!」というコメントも。
【跳兎(とと)さん賞!】鳥RさんによるMinecraft国家のWebサイト
跳兎(とと)さん賞は、オリジナルWebサイトを制作した鳥Rさんに授与!


「神萘(シェンナイ)」と名付けた自分のMinecraft国家への情熱に、突き詰める愛を感じたとのこと。こだわりの強さに、「クリエイターとしての魅力を感じた」とのコメントも!
【技術が一番すごかったで賞!】cheeseさん「Battle Tower」
技術力賞は、Unityでポケモンゲームを制作したcheeseさんの「Battle Tower」に決定!


他の制作と並行し、さらに自分でバグを直しながら作り上げた姿勢も高評価!
制作期間、実装力、世界観、すべてにおいて群を抜いた完成度で、コメント欄には実際に遊んだ生徒の声が続出しました。「どんどん自分で解決していて、ほんとにすごい」との称賛も。
【プレゼンが一番上手かったで賞!】RUMI.さんによるナレーション付き発表
プレゼン賞は、RUMI.さんの作品発表が堂々受賞!

ナレーションへのコメントも多数!生徒の中にはRUMI.さんファンもいるんだとか。

Unityクラス・自由枠クラスそれぞれで作品を発表されました。
自作の音楽、そしてプロのような語り口で、MCたちからも「仕事を頼みたい!」との声が。
担当のとよ先生からは、「前からいる生徒だけど、特に今回は人間力のレベルアップを感じました。」と、クリエイターとしての成長も見られる作品も。
【観客賞】りんごまんさん「集めて作るゲーム」
観客の投票によって選ばれたのは、りんごまんさんによるUnityゲーム「集めて作るゲーム」です!

石1個と木1個でパソコンを制作できる設定。

こだわりを感じるクラフト画面。頑張ったことは「UIの作成」とのこと。
「石1個と木1個でパソコンを作れる」と、世界観の面白さも観客の心を引きつけました。
続いて、タイピングバトルの表彰です。
【タイピングバトルチャンピオン】
1位:へのさん
2位:りさとくん さん
3位:ブラウンさん
MCのお二人や各講師陣からは、「もう殿堂入りでは?」と声が上がるほどの堂々たる優勝でした!
文化祭の締めくくりには、運営に関わった先生たちから生徒の成長ぶりを称えるメッセージが寄せられました。
配信の裏側を支えたり、設営やコメント対応に奔走したりと、表に見えない部分でも多くのサポートがありました。「次のタームではさらに盛り上げたい」「生徒たちが主体的に動いている姿が頼もしい」といった声が寄せられ、文化祭を通じて先生たち自身も大きな刺激や学びを得ていたようです。
先生も生徒も、関わった全員が参加者として楽しみ、支え合いながら創り上げた2日間でした!

そんな熱量あふれる文化祭を支える理念について、続いてはITeens Lab代表・共同代表のインタビューをご紹介します。
ITeens Lab代表インタビュー
今回はITeens Lab 代表 コバ先生(古林 侑樹先生)・ITeens Lab 共同代表ドゥー先生(近藤 悟先生)のお二人に、ITeens Labの理念やカリキュラム、文化祭への想い、そして今後の展望についてお話を伺いました。
ーITeens Labでは、「主体的に生き抜く力を育てる」を理念の一つに掲げているそうですね。代表としての思いや、主体性を育む取り組みについて教えてください。
ドゥー先生:カリキュラムにおいては、基礎的な内容に触れつつも、ある程度進んだ生徒はどんどん自分のやりたいことにシフトしていくのが特徴です。
「今日は何やる?」「オリジナル作品つくります〜」のようなやりとりもあったりして。先生は前に立って一方的に授業するというより、生徒のやりたいことをサポートするスタイルです。
たとえば、カリキュラム外でのMinecraftワールド制作においては、僕らが事前にルールを決めることはしていません。自然発生的に自治が生まれ、子どもたちの成長に繋がっていると感じます。問題が起きたら、直面して一緒に考える。そのプロセスを大切にしています。

ITeens LabサーバーのMinecraftクリエイティブワールド
コバ先生:代表の思いとしては、立ち上げ当初は、日本のIT教育に少しでも貢献できればと考えていました。地域や機材の環境差、教える先生による指導のばらつき、そんな不平等を少しでもなくしたくて、ITeens Labを始めたんです。
でも年数を重ねるにつれ、今は目の前の生徒たちをもっと大事にしたい気持ちが強くなっていますね。教育業界全体にどうアプローチするかというより、ここで出会えた子どもたちの文化や空気をもっと良くしていきたいです。
ーITeens Labの生徒や、スクールの雰囲気について教えてください
ドゥー先生:ITeens Labは他のプログラミング教室と比べると少し年齢層が高めで、小学高学年〜中学生くらいが中心です。
ただ、プログラミングスキルがゼロでも、ファイルの保存やブラウザのタブ切り替えができたり、アカウントの仕組みを理解していたりと、パソコン操作に慣れていれば色々なことにチャレンジできます。
とはいえ、最近は、「プログラミングって何もわからない」というところから入ってくる生徒は少なくなってきましたね。体験会でも未経験者は減ってきていて、すでに他スクールで学びつつ、2つ目としてITeens Labに来るケースも増えています。

プログラミング基礎クラスではScratchやUnityを中心に学べる。
プログラミング基礎から始まって、Webコーディング、そしてUnityへ進んでいくのがスタンダードになっています。今やUnityクラスだけでも50〜60人は在籍しています。Unityをやるのは当たり前のような雰囲気ですね。
ー最近は生徒や講師陣がグローバル化しているとお聞きしました。
ドゥー先生:最近は、全国・海外からの参加者も増えています。
ITeens Labの授業は基本的に自宅から参加するスタイルです。そのため、アメリカ、シンガポール、インドなど、海外在住の先生もいます。英語ネイティブの先生も少しずつ増えているので、今後は英語で行う授業や、英語圏の生徒の参加も展開していこうと考えています。
インドやパキスタンからのエンジニア参加、カナダに行く先生、ロシアからのトライアル生徒や、中国からファイアウォールの問題に直面した生徒など、エピソードには事欠きません。

国や言語など、グローバルな話題に興味津々の生徒も多数
ー生配信では、生徒が画面共有に手こずる場面もありましたが、「先生が画面共有しようか?」「ゆっくりでいいよ」と、優しくフォローする姿が印象的でした。
ドゥー先生:
発表の持ち時間が予定より延びてしまうこともありますが(笑)、先生たちは子どもたちの作品や進行を把握し、タイミングを見ながら自然にフォローし合っています。全員で協力して運営する空気感もITeens Labらしさのひとつです。
講師として重視しているのは、技術力だけではありません。それ以上に大切なのは、生徒と一緒に遊びながら学べる姿勢です。採用の際も、コミュニケーション力や生徒に寄り添う力を重視しています。

文化祭を盛り上げてくれるMCの先生たちも、生徒たちのギャグやノリを理解したうえで、場の雰囲気を盛り上げてくれます。
講師陣はエンジニアコミュニティからの紹介のほか、元生徒の高校生や大学生がそのまま先生として参加してくれることもあります。年齢や距離を越えて自然に学び合える関係性が築けるのも、ITeens Labの強みですね。

生徒達の間で「言語」が流行中。先生が分かってくれていることで、安心して自分を出せます。
ーITeens Labにとっての文化祭の位置づけについて教えてください。
コバ先生:
文化祭は、いまITeens Labのなかで最も価値のある取り組みだと思っています。
日々の授業で「何を教えるか」も大事ですが、文化祭ではコミュニティとしての一体感が生まれるんです。画面越しであっても、お互いに涙を流すほど感動する瞬間がある。ネット上とは思えないほど、温度のあるやり取りが存在しています。
また、ITeens Labは生徒にとってのサードプレイスでもあります。プログラミングスクールの多くに「居場所」的な側面はあると思いますが、ITeens Labは特にその色が強く、学校には通いづらくても、ここではいきいきと活動する生徒も少なくありません。

お茶を囲んで(!?)会話を楽しむ生徒達
ドゥー先生:
文化祭は、ITeens Labが授業を受ける場所としてだけでなく、自分たちで活動する場所でもあることを感じられる大切な機会です。
配信も最初は限定公開からスタートし、リスク管理も徹底したうえでリアルタイム配信や一般公開へと広げてきました。
リスク管理で言えば、テキストコミュニケーションにも注意が必要です。ITeens Labでは文化祭をはじめ、普段の授業や企画のやりとりもDiscordを使って進めています。生徒同士で意見のぶつかり合いがあったときには、職員室で先生と生徒が話し合うこともあります。

「通学先」のMetaLifeには、受付や職員室、自習室や応接室などがある。
文化祭は、日々の積み重ねが形になって表れる場所です。保護者の方にとっても、見えにくかったスクールでの学びや成長が、文化祭を通して伝わるのではないでしょうか。
ー今後の展望について教えてください。
ドゥー先生:今後はもっと生徒主体の活動を増やしていきたいです。生徒が先生と打ち合わせして、Googleフォームを作ったり、企画書を書いたり……もう実案件で働けますよね。
文化祭では、前回初めて生徒企画を取り入れたのですが、「やりたい人ー?」と聞くと自然と手を挙げる子が増えてきました。生徒にとって貴重な経験になりますよね。
保護者の方も、もっとコミュニティとして巻き込んでいきたいです。ゲームしすぎ問題やネットの怖さを心配する声もありますが、「一緒に遊んでいたら大丈夫」の感覚を共有していきたい。実際、娘さんよりお父さんの方がハマっているご家庭もあります(笑)。

コバ先生:
保護者のみなさんの参画については課題感もありますね。生徒と僕らの間では、文化祭はタームの集大成であり、すごく盛り上がるイベントなんですが、保護者の方にとっては共感しづらい部分もあります。
生徒のノリをどうやって共有するか、どう巻き込んでいくかが今後の課題だと感じています。
とはいえ、ITやクリエイター系のお仕事をされている方を中心に、一緒に楽しんだり作品を発表してくださるケースも増えてきました。大人が楽しむ様子がもっと広がっていけば良いですね。

1年を3学期に分けたターム制。4ヶ月に1度の文化祭で成果物を発表する。
ー最後に、読者へのメッセージをお願いいたします!
コバ先生:
最近のITスクールでは、やりたいことをサポートするスタンスが主流になりつつあります。ペイントツールを使って遊ぶのと同じように、ITを使った表現も気軽に楽しんでみてください。
図工のようでもあり、音楽も文学も数学的な表現もできる。ものづくりの視点で見れば、どんな分野にも広がっていく可能性があるのがITです。

「とにかく、まずは楽しんでほしい」と語るコバ先生は、ラッパーとしての経歴も。
僕も作品を提出していますが、生徒とは「お、やってるね!」と、同じ目線になれる空間です。 そんな空気の中に、保護者の方もぜひ一緒に入ってきてもらえたらと思っています。
ドゥー先生:
高度情報化社会では、ITスキルだけでなく、コミュニケーション力や人との関わり方もとても大切です。
最近は、無料の教材も多くありますが、子どもたちにとって何より大きな影響を与えるのは「誰と、どんな環境で学ぶか」。仲間の作品を見て「次は自分もやってみようかな」と思えたり、そこから友達が増えていったり。そんな自然な広がりが、ITeens Labの魅力の一つです。

インターネット上でも、社会性を育む経験は重要です。バーチャル空間の中で、他者と関わり合いながら安心して過ごせる力を育てていけたらと思っています。
また、大人の役割としては、「教えなきゃ」と思いすぎずに、子ども達と一緒に学ぶ気持ちで関わることがポイントです。最先端の技術は、大人でもすべてが分かるわけではありません。

生徒と一緒に学び続けるドゥー先生。オリジナル作品も遊び心満載。
子どもたちが青春できる、ITeens Labならではの文化祭
文化祭を通して印象的だったのは、生徒と先生の距離の近さ。オンライン上とは思えないほど自然で、まるで同じ空間にいるかのような空気感が流れていました。どんな風にこの関係性が育まれているのか伺ったところ、ITeens Labは子どもたちがITを通じて青春できる場所を目指して設計されているとのこと。
プログラミングというと孤独なイメージを持たれがちですが、ITは情報のやり取り、つまり、人と人をつなぐもの。だからこそ、ITeens Labは作品制作や学びを通じて友達ができたり、夢中になれたりする体験を重視しているのです。
先生たちも、生徒たちと同じ感覚で「ネットでのコミュニケーションって楽しいよね」と共感してくれる存在。全国に点在する先生や生徒が連携し、文化祭を一緒に作り上げていました。
今回の第15回文化祭でも、新たな取り組みが続々と登場しましたが、これからのITeens Lab文化祭も、まだまだワクワクが待っていそうです。



Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(レポート)わくわくドキドキ!プロクラ万博2024 TOKYOの様子をご紹介!
プロクラ万博2024 TOKYOは、「マイクラ」の世界でプログラミングを学べる「プロクラ」恒例の大イベント。2024年12月22日、GMOインターネットグループ 渋谷フクラス16F「G...
2025.05.30|大橋礼
-
熱気最高潮!「VIQRC/ V5RC Japan Cup 2025」世界とつながれるロボット大会をレポート
2025年3月20日(木)、品川インターシティホールにて「VIQRC Japan Cup 2025」と「V5RC Japan Cup 2025」のジャパンカップ2025が同時開催されま...
2025.05.30|大橋礼
-
『ロボッチャ®ジャパンカップ2024』大会レポート|ボッチャ×ロボット!STEAM力を育てるスポーツ競技の魅力を探る
パラリンピックの正式種目としても有名な「ボッチャ」をロボットで競う大会『ロボッチャ®ジャパンカップ2024』が、開催されました。今回はたくさんの写真と共に、2025年3月16日に行われ...
2025.05.30|大橋礼
-
合宿は本物の科学に出会い、自分の可能性を見出す場!「子どもの理科離れをなくす会」春合宿レポート
まだプログラミング教育という言葉が広まっていなかった15年以上も前から、ロボットを通して科学教育を行っている『子どもの理科離れをなくす会(以下、理科会)』。今では全国に60教室、約60...
2025.05.26|工樂真澄
-
【レポート】第14回ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室全国大会|白熱した大会を見てみよう!
2024年8月24日(土)、東京大学安田講堂にて「第14回ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室全国大会」が開催されました。27,000名以上の生徒の中から、予選大会を勝ち抜いた2...
2025.05.30|大橋礼




















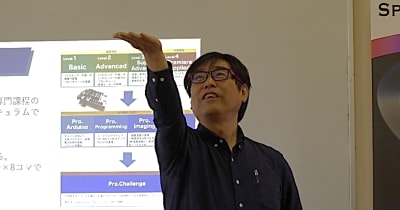
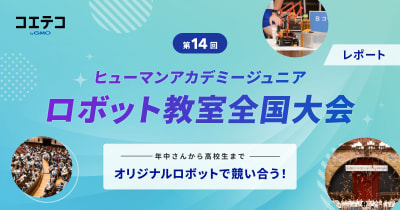
不協和音をうまく活用して、キャラの雰囲気とマッチさせてくれましたね!